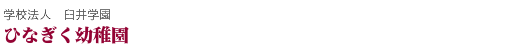本日、5月のおたよりと共に、今年度の年間予定表を配布しました。見やすいところに貼ってご活用ください。
さて、ざっと一年間を見わたしてみましょう。幼稚園生活の中にいくつかの行事が組み込まれていることが分かります。例えばうんどう会、例えばクリスマス…。これらの行事を日本の子ども達は幼稚園で殆んど経験しますが、その内容は地域性やその園の考え方によって違いがでてきます。それでは、ひなぎくは行事をどう考えるか? 当園の行事の考え方の基本をお伝えしたいと思います。
1.参観
「幼稚園での我が子の様子を知りたい」というご父母の声にお応えして、実際の幼稚園生活を見、保育についての理解を深めて頂きたいと思います。ただし、子ども達にとって多くの目に「見られている」というのはとても負担に感じるもの。そこでたとえ参観であっても「子どもにとって楽しい、よい時間に」と考えるのがひなぎくです。わらべうたやゲーム、お弁当を一緒に食べる…とお父さん、お母さんに参加して頂くことで、「あ~たのしかった!」という気もちを子ども達は味わえます。大人も子どもも一緒になって遊ぶと自然にお友達の輪も広がります。6月の「お父さんと遊ぶ日」も然り。同じ時間に幼稚園に集まった大人も子どもも「共に楽しむ日」にいたしましょう。
2.お泊まり保育、うんどう会、ひなぎく祭…
これらの行事から、「ひなぎくは行事を打ち上げ花火のような1回限りのイベントではなく、毎日の保育の延長線上に位置づける」という考え方を分かって頂けたらと願っています。ひなぎくではそれぞれの行事の中味を決めるのは子ども達の遊びや好きな絵本、その年その年の子ども達の興味や関心です。先生達の仕事は子どもがやりたい!と思っていることに気づき、それが子ども達の力で実現できるように教材を提供し、ヒントを与えて支えながら環境を整えていくことで、毎年内容が違うのもそのためです。そして当日を迎えますが、その後も「面白かった」「楽しかった」故に、その余韻を楽しむが如く、延々と子ども達が満足するまで日常保育の中でその活動は続いていきます。その時間と場所を確保してあげることで、その行事は、その子にとってより意味のあるものになるといえるでしょう。
大人の都合で「もう、終わり」と切ってしまわないので、「今度はぼくがやってみたい」という気になった人にもチャンスがめぐってきますし、あこがれの気もちで見ていた人も学年を超えて「やってみる」ことができるのです。
「行事は、見せるためのものではなくて、子ども自身が楽しみ、その自発性を育てるために!」を合言葉に今年度もすすめて参ります。
そして3月には、我が子がどんな成長した姿を見せてくれるか、それを共に楽しみに一日一日を大切に歩んで参りましょう。そして私達大人も負けずに親として、教師として成長したと思える一年に致しましょう。