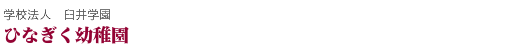11月19日、前園長
村松偕子先生が神さまのもとに逝かれました。
お元気な頃は、保育の現場に毎日いらっしゃり、子どもたちのことだけでなく、私たちのこともあたたかく、時に厳しく見守って下さいました。園舎にいらっしゃらなくなってからも、目の前のご自宅から、毎日園庭に響く子どもたちの声や歌声に耳をかたむけ、心を向けて下さっていました。今、悲しみの中にある幼稚園ではありますが、子どもたちの声を絶やさず、毎日の保育に励むことが、ばあば先生の一番喜ばれることでしょう。今までとかわらずに、みなさんと一緒に歩んでいきたいと思います。
早速、保育の話をしていきましょう。
幼児期の運動能力を高めるには、全身運動が大切で、たくさんの動きが含まれているのが「おにごっこ」というお話は以前しました。では、心をたくさん動かし、人とのコミュニケーション能力を育んでいくのに大切な経験は…「ごっこ遊び」と言われています。病院ごっこ、おうちごっこ…等たくさんありますが、その中の一つがひなぎく祭でのお店屋さんごっこですね。毎年お店屋さんが開店しますが、同じお店屋さんはありません。それは、こどもたちの「今!」楽しんでいるごっこ遊びから考えて、話し合ってつくられていくものだからです。
始めは小麦粉粘土でパンづくりを年長組の子どもたちが楽しんでいました。
ある日「ねえ、パン屋さんやらない!?」と一人の女の子からの提案。そして「いいねえ~やろう!」と仲間の賛同。ここから始まりです。パンをたくさん作ったり、色をぬったり、看板を描いたり…役割分担がうまれ、協力をしていきます。その中で、まだできあがっていないけど、早くお客さんを呼びたかったり、パンづくりがあきてしまったり、様々な友だちの心の動きが見られます。色々な友だちの考え方に向き合うために、そこに話し合いがうまれるのです。
準備ができていよいよオープン!今度は自分たちより小さな年少・年中組の子どもたちと関わります。同学年の友だちとは違いますね。言葉をわかりやすくしたり、優しく話しかけたり…実際に関わって学んでいくのです。
年中組も…年中なりのお店屋さんごっこが始まっています。
そんな時、年長のお店屋さんに呼ばれていくと…本物のようにおいしそうな様々なパンの種類に「わ~!!」とあこがれの眼差し。そしてお店屋さんの応対も親切でスムーズで、自分たちとは何かが違うのです。すごいなあ、素敵だなあとあこがれる気持ち、大切ですね。そこから「もっとこうしてみたい!」と更に考えが膨らみ、遊びが広がっていくのです。
年少組は…オムライス屋さんやおすし屋さんをやっています。
(きっとお家でおいしく食べたのでしょうね)でもまだお客は教師だったり、お店屋さんと言っても店員は自分一人だったりです。年長組のお店では、その雰囲気にやや圧倒気味。でもおいしそう~!店員さんに教えてもらいながら、担任のやり方を真似しながら、パンを買います。あまりにもおいしそうで、本当にちぎったり、ドーナツを半分こにしてお友だちと分け合ったり…「本当」と「ごっこの境界がまだあやふやなのが年少さんの発達段階でもありますね。(さすがの年長もちぎられたパンにビックリ!でもそれ位おいしそうに見えたということで、嬉しくもありました)
仲間に認められながら、遊びの中で役割分担やルールを決め、時に折り合いをつけて一緒に遊びをつくっていくこと―ごっこ遊びには、これらの友だちと関わる力に必要な大切な要素がたくさんはいっているのです!第二アドベントです。クリスマスを待つ生活の土台にもごっこ遊びがあります。天使ごっこ、宿屋さんごっこ、馬小屋の動物ごっこ…よく見て、よく聴いて、感じて、とりくむ毎日の中で、あたたかなクリスマスをみなさんで一緒に迎えたいと思います。