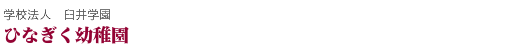雪の日々
2月には2回大雪が降り、園庭の積雪は一時40cmにもなりました。雪が積もって大喜びなのは子ども達。今年は、かまくらや雪だるまがいくつも園庭に立ち、山からのそりすべりと雪合戦に興じる子どもたちの歓声が連日響き渡りました。奇しくもソチオリンピックの開催と重なり、そりは佐藤先生(年少組の体操とサッカー教室担当)作の山の上のジャンプ台からのジャ~ンプ大会! へ、アイスホッケーは本物のスティックとパックが届いて大盛り上がり、子どもたちは砂場のスコップをスティック代わりに、凍った園庭で夢中で本物のパックを追いかけました。静かに降り積もる雪は美しいものの大人はつい雪かきや交通網の心配に気を取られますが、それよりも子ども達との雪遊びの楽しさの方がはるかに勝っていたひなぎく幼稚園での雪の日々でした。
お手伝い
そのジャンプ台を作るべく、雪を手押し車に乗せて運んでいた佐藤先生を見て、お手伝いを買って出たのが年長組の男の子達。砂場用の小さい手押し車でやってきて、何回も往復しては重い雪を運んだのです。そのうちに何人も「手伝おうか」「私もやるよ」と集まってきて、交代で「うんしょ、うんしょ」と雪運びをしました。みんなのためにジャンプ台を作るんだという目的も共通に掌握された上での活動(遊び)でした。ほどなく、年長組がお部屋に引き上げていくと、そこにいたのは年中組。佐藤先生が誘っても表情は今一つ、力も今一つで、重い雪を乗せた車を押すとバランスが取れずふらふらして楽しいどころではないのです。体力、技術共に今は足りず、「やりたいのにうまくいかない」というのが年中らしい実情だったのでしょう。年少組に至っては、ただただそりで遊ぶばかり。皮肉なことに、一番タイミングよく園庭に出てきて、そりジャーンプ! を佐藤先生と心ゆくまで楽しんだのは、年少組でした。
それぞれの学年の特徴
これはほんの保育の一コマですが、それぞれの学年の特徴が如実に表れていて面白いなあと思いました。一年前には、お母さんと別れるのが心配で泣いていた年少さんが、もう今ではお友達とキャッキャッと笑い合って果敢にもそりに挑み、そのスリルを楽しんでいます。お友達と一緒に、先生と一緒に共感し合って、という点が大事なポイントですね。
年中組さんは、お店屋さんごっこでも砂場のダム作りでも製作でも、ボール遊びでも組み立て体操でも、年長組さんのようにやりたいけど技術的に及ばずできないという経験をたくさんしてきました。でも、周りが見えて、やってみたいなと思うのも成長の証。お友達と力を合わせようにも、それぞれの主張と主張がぶつかり合ってうまくいかない。たからこそ、どうしたらいいのかをお友達と一緒に学び合った一年でした。
そして、卒園を目の前にした年長組は、自分で気づき大変そうな人のところにお手伝いに行ける。みんなのために、と喜んで力を出すことができる。こんな「思いやり」の心がもてるまでに成長しています。人は一人では育たない。まず、乳児期に可愛がってくれる家族がいて、そして、周りにお友達がいたからこそ、笑い合い、困った時には話し合い考え合う。そして、幼児期を終える頃には、他者に対する思いやりの心が持てるようにまで成長できる。仲間がいたからこそ育ち合うことができたことに感謝し、これからも、小学生になってもお友達を大切にする人になってくださいと願ってこの年度末を過ごしています。
今年度も保護者の皆様には、ひなぎくの保育に対する深い理解と、あたたかいご協力を頂きましたことにここに厚く御礼申し上げます。