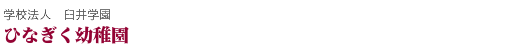先学期に、目白の教会を通して福島から復興を願うヒマワリの種が届きました。仲介役はすみれ組担任の松下先生。年中組の子ども達が保育室の前にプランターを出して大切に植え、育てました。夏休み前に1つ、2つと咲いて幼稚園中の子ども達を喜ばせてくれたヒマワリは、その後も大きく花開き、この猛暑、酷暑の日々にも力強く咲き続け、今はたくさんの種をつけて子ども達の登園を待っています。
園舎に一歩入ると…
また、今年も夏休み中の幼稚園に連日職人さん達が来て、大屋根の塗装、園庭西側通路のフェンス新設、園庭アスレチックの高圧洗浄と消毒を行いました。この灼熱の中、黙々と作業を行う職人さん達には、本当に頭が下がりました。一方、園舎に一歩入ると、階段からホール前までの床の貼り替えと、年長組の保育室のカーテンが爽やかなグリーンになったことに気づかれると思います。気分も一新、2学期からの保育がますます楽しみになってきます。建物に入るとパッと目に入る床やカーテンのリフォームはこんな風に、空間の雰囲気を新しくするものかと実感しました。
乳幼児期が基礎工事の時
その一方で、私達が尊敬する児童精神科医の佐々木正美先生が、子育てについての著書「子どもへのまなざし」(福音館書店)に書かれていることを思い出していました。ここに、16~17ページを抜粋してご紹介します。
『育児では、その基礎工事が乳幼児期にあたるということを、よくわかって頂きたいと思います。乳幼児期が基礎工事の時で、その後の時期を、たとえて言いますと小学校、中学校、高校、大学、あるいは大学院、留学などというのは、後から造っていく建物の部分です。そういう意味から申しますと、小学校や中学校くらいが床や柱かもしれませんし、高校くらいになりますと外装の工事とか屋根の瓦など、そんなものかもしれない。大学や大学院、留学なんていうのは、内装工事かもしれませんし、あるいはカーペットや家具かもしれない。まあ、こんな風に思って頂くといいのです。そうするとみなさん、後からやるものほど、やり直しがきくということが、お分りになるでしょう。カーペットなんか、後からいくらだって、敷き替えができます。家具なんていうのも取り換えられるのです。人の目にとまるのは、あとからやったところなのですね。ところが、基礎工事なんていうのは残念ながら、建物が建った時には、なにも見えなくなってしまうのです。けれども、しっかりした建物かどうかというのは、確かな基礎工事なしには考えられないのです。(中略)基礎工事に関心を持って、床をめくってみようなんて人はいないのです。そんなところには誰の目も向かないですね。けれども、一度ことがあった時、基礎工事がどれくらい建物の命運をけっするかということは、よくおわかりでしょう。(続く)』
ひなぎくの保育を実践していきます
この基礎工事とは安心できる環境で仲間とよく遊び、自信と意欲と人と関わる力を子どもの中にしっかり育てることに尽きると私は考えています。2学期の行事ももちろん楽しみですが、それはこの毎日の楽しい園の生活の延長線上にあるもの。そのことをしっかりと心に刻み、教職員一同、ひなぎくの保育を実践していきます。保護者の皆様ともご一緒に心を合わせて共に歩んで参りましょう。