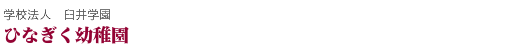みんなは今頃どんな夏休みを過ごしているかなあと想像しながら、今日も幼稚園では、日直の教師2人が保育室の窓を開けて園舎に風を通して掃除をし、小鳥や植物のお世話をしています。そして、朝の仕事が一段落すると2学期の保育の準備にとりかかります。 何しろ2学期は、子ども達の遊びが日に日に充実する学期。その遊びの充実があるからこそ、皆さんが楽しみにしているひなぎく幼稚園の秋の行事が生まれてくるのです。今学期も、子ども達自身が幼稚園での遊びを通してたくさんの経験を積み重ねてほしいと願っています。
ところで、「遊びが大切」と一言で言っても、それは一体どういうことなのか?
私は、乳幼児期には自分が「遊ぶ」という実体験からしか学べないことがあると確信しています。
たとえば年少組は楽しそうに遊んでいる年長組のお兄さん、お姉さん達の姿をよく見ていることがあります。ただ見ているだけです。でも私はその姿を尊重します。「楽しそうだな~」「自分もあんな風にしてみたいなあ~」と、そんな風に言語化していないかもしれませんが、その憧れの気持ちを味わっているのが分かるからです。私はよくこの状態を「見て参加している」とか「心を動かしている」と表現して、子どもの内側を見ようと先生達にも話します。この気持ちが熟せば、いつかこの子どものタイミングで内側から遊びへと向かっていく。よく、ひなぎく幼稚園で「子どもが自分から動き出すまで待ちましょう」とお話しすることに通じる理由です。
ところが、いざ、自分達でやろうと遊び始めたところで、そうは簡単にはいきません。
ひなぎくの子ども達の得意中の得意、ごっこ遊び一つとってもその道のりには大変な苦労があります。まず、「~しよう」「ここは~ってことね」という企画立案が仲間に「いいよ~」と承認されなくてはなりません。幼稚園でのごっこ遊びはセットされた状態からではなく、お友達と一緒に一から創っていく遊びです。自分の意見を言い相手の考えを聴く相談もしないと前に進まない、役割分担も必要。「役の譲り合い」を通して「順番」という社会のルールや思いやりの心も学んでいきます。そして、最終的にはごっこ遊びの最大の醍醐味、協力する楽しさを経験できるのです。
そこまで一足飛びに行かないからこそ子ども達は苦労する。
悔しい思いも、言ってはいけないことを言ってハッとすることも、しまったと思うことも、思わず手が出てしまうこともある。一人でぐっと耐える時間も味わう。よく私が「葛藤」という言葉を用いてお話するのは、こういう時のことです。この「葛藤に時代」は主には年中組にかけてだと考えています。
今年の夏も教師達は研修によく励みました。多い人で12日間研修に参加しています。それも、自身の保育観を問うものや、教師自身がideaを出して想像の翼を広げるようなcreativeな経験ができる研修を選んで参加していることを誇りに思います。なぜなら、その様な実体験を積んでいる教師達にこそ真の「遊びを大切にする保育」が行えるからです。
今学期もどうぞ、このようなひなぎくの保育をご理解頂き引き続きご協力ますようお願い致しします。